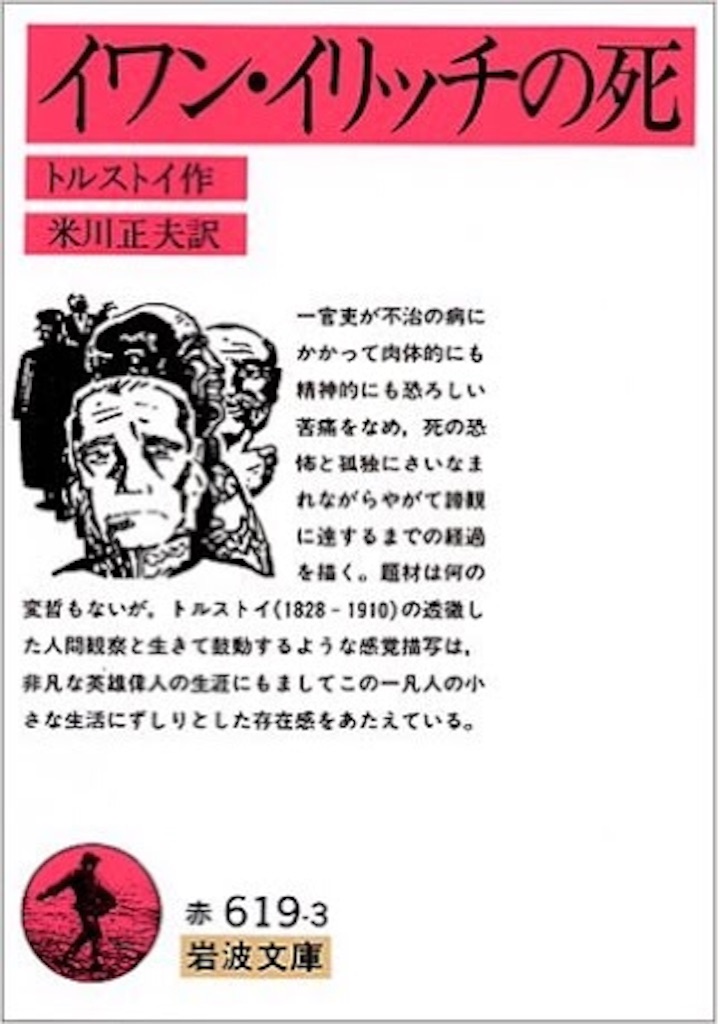「イワン・イリッチの死」トルストイ
自分自身の死を想像したことは誰しも一度はあるのではないだろうか。そしてその時人は往々にして突然で劇的なものを想像しがちである。
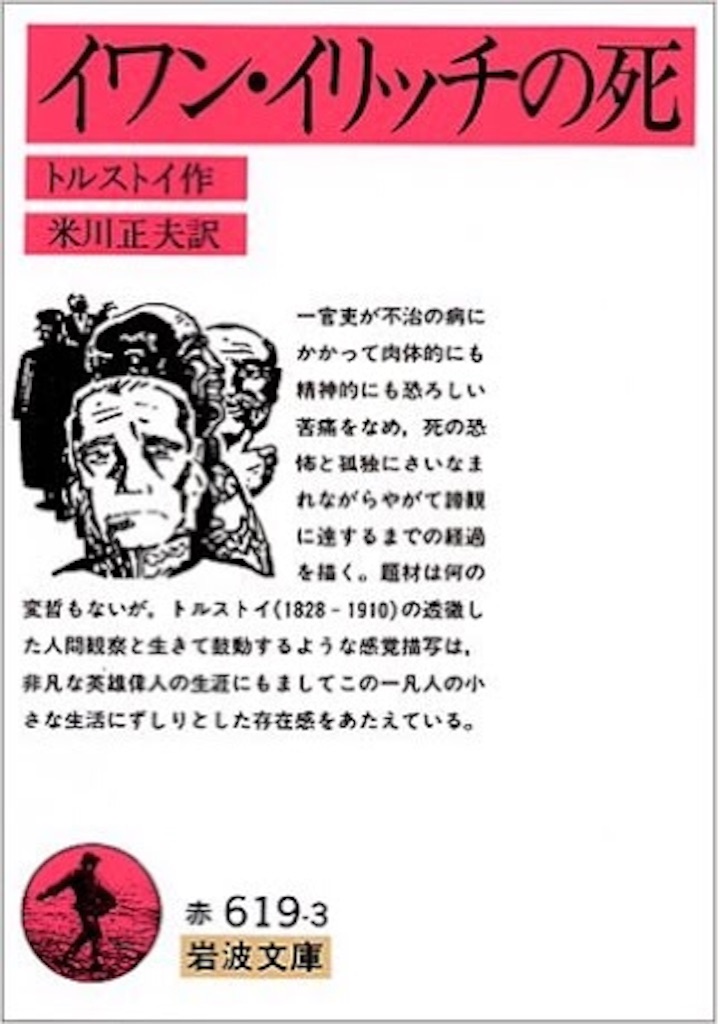
天文学者であるChris impey氏の著作“How It Ends“に次のような一節がある。
「人生がコンサートのようなものであったとしても、その結末はクレッシェンドで終わることはなく、大抵の場合は楽器の調子が外れ、演奏家達が列を乱し、音楽が次第に消えていくものだ。…残念ながら人生はめったに芸術には似ていない。」
誰がこのような結末を望むだろうか?今回の小説の主人公イワン・イリッチの死も前述のような芸術には程遠い死であった。そして、それは私たちの「死」についても同じなのである。
俗世的な成功を収め、官吏として「気持ちの良い」生活を享受していた主人公イワン・イリッチはふとしたきっかけから不治の病を患う。「生」への執着と嫉妬は彼に身体的な苦痛だけでなく精神的な苦痛をも与える。その中で主人公が死への恐怖と孤独に耐えながら達観するまでを描く。ーー
まず、この小説は主人公であるイワン・イリッチの葬式の場面から始まる。そこで描かれる参列した主人公の旧友や家族、同僚達の心理描写には文豪トルストイの手腕が遺憾なく発揮されている。
「…彼はイワン・イリッチの最後の様子などを興味ありげな様子で根ほり葉ほりききはじめた。それはまるで死というものが、イワン・イリッチのみに特有の変事であって、自分にはまるで関係がないというようなふうであった。」
「…『三昼夜の恐ろしい苦しみと死、それはすぐにでも…このおれのことになるかもしれぬ』と彼は考え恐ろしくなった。…けれどいつものような考えが助けに現れた。…これはイワン・イリッチの身に起きたことであって、自分のことではない。…自分の身に降りかかるなんて、到底あり得べからざる話だ。そんなつまらぬことばかり考えていると、陰気な心持ちに取り憑かれるばかりだ。…やめておいたほうがよいのだ。」
つまり、トルストイはこれから始まる個人的な経験としてのイワン・イリッチの死を、私たち読者が抱くであろう「自分も経験するのではないか」という不安感と「死んだのは自分ではない」という安心感の二つの相反する考えを参列者という登場人物の心理描写を通して代弁することにより、普遍的な経験に変貌させたのである。トルストイが読者の心理を読み取ることの妙を得ていたことが伺える一節である。
第2章から3章にかけては、イワン・イリッチが如何にして「気持ちの良い」生活を築き上げてきたのかという半生が語られる。
カードゲームや上品な友人との晩餐会を嗜み、子育てや家事、生活の不満を述べる妻から生活の愉快さ、上品さを守るために「もし反抗や不平に出会えば、すぐさま勤務という別世界に引っ込んで、その中に愉快さを見出すのであった」。このようにして、彼は官界での出世を掴んだのであった。
しかし、第4章以降からはふとしたきっかけから彼は体の不調を訴え、その後階段から転げ落ちるように病状が悪化してゆく。友人との談笑や勤務が突如として襲った病から彼を救うことはなかった。
イワン・イリッチは病床にて回想する。「世間の目から見ると、自分は山を登っていた。しかしそれと同じ程度に「生」は足元から逃げ出していたのだ。」
加えて、幾度となく描写される横腹の痛みには、鬼気迫るものがある。
「突然公判の最中に、例の横腹の痛みが、…一切の頓着なしにじりじりと吸うような例の仕事を始めるのであった。イワン・イリッチは…考えまいと努めた。けれども、痛みは自分のするだけのことを続けた。…彼の体は棒のように固くなり、目の中の光は消えてしまう。」
「その三日間、彼にとっては時間というものが存在しなかった。彼はその間ひっきりなしに、決して打ち勝つことのできない、目に見えぬ力に押し込まれた、黒い袋の中でもがき続けた。ちょうど死刑囚が首斬人の手の中で暴れるように所詮助からぬと知りながら暴れまわった。どんなに一生懸命もがいても、次第に恐ろしいものの方へ近寄ってゆく、それを各瞬間ごとに彼は感じた。」
そして死の間際に、彼は自らの積み上げてきた世俗的な生活の虚偽を認め死の代わりに光を見る。そして、主人公の命の灯火が消えると同時に物語の幕は降りる。
この残酷なまでにリアリティーのあるまさに「芸術からかけ離れた」死を淡々と描いた本作は、現代の日本に欠けてしまった重要なピースを補完するものではないのか、と私は直感的に感じた。
トルストイは敬虔なキリスト教信者であり、思想家であった。イワン・イリッチの死においてトルストイは家族や友人からの愛などではなく、思想で以って彼の死に救いを与えた。(さらに詳しい彼の死生観については彼の晩年作「人生論」を参照することをお勧めする。)
すなわち彼は本作においてあくまでも「死」を個人的に乗り越えるべきものとして描いたと言える。(妻から逃げ出し、客死したトルストイらしい結末とも言えるかもしれない。)
これは、現代に生きる我々にとって、あまりにも厳しく酷なメッセージではないだろうか?
思想なき日本では、今後も高度化した医療技術の中でさらにこの「芸術からはかけ離れた死」の形が増加し続けていくであろう。そして、さらに「死」と「生」の境界線は曖昧になっていくだろう。
加えて、マスメディアや多くの著作では「死」をまるで芸術作品のように、家族の愛によって乗り越えるものとして取り上げられがちである。
その中で我々は近い将来に直面するであろう「死」に何を以って救いを求ればよいのであろうか?我々が個人として「死」に光を見い出すことはできるのであろうか?
この享楽主義的な現代に「メメント・モリ」という戒律はあまりにも異質であろう。
しかし、そしてこの戒律は「生の肯定」という陳腐な教訓として受け入れるべきではないと思われる。
この戒律から我々がせめて自覚すべきことは「死」を許容しそれを乗り越える新たな思想を現代の日本は必要としているということであるのではないだろうか。