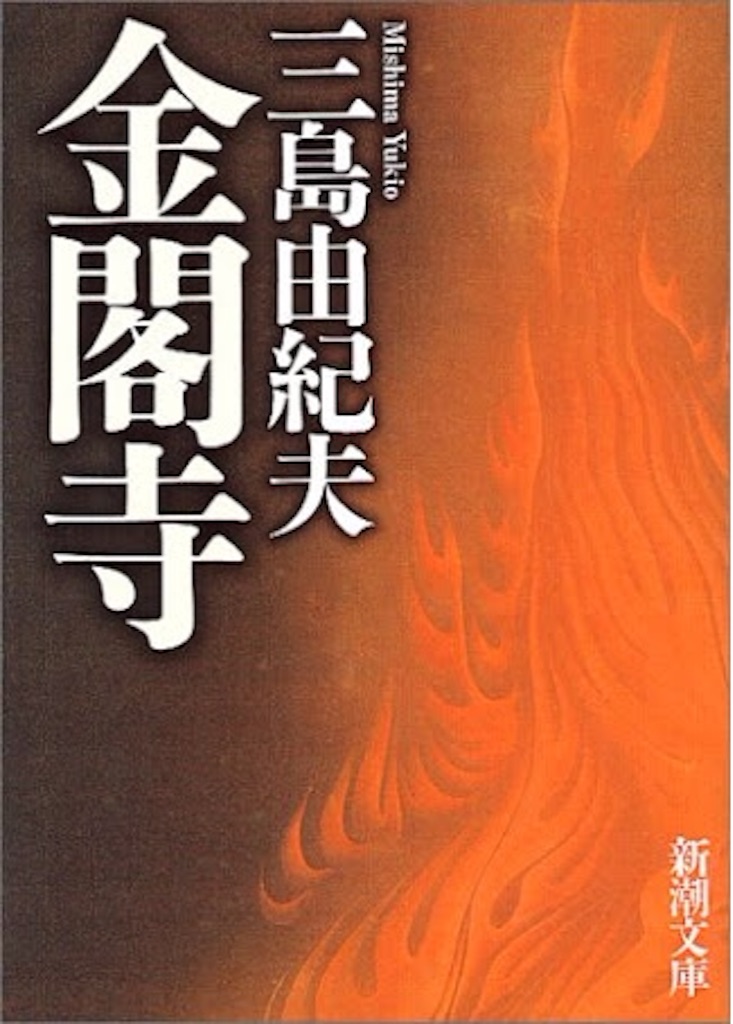「金閣寺」三島由紀夫
1950年7月、ある一人の僧侶の放った炎によって金閣寺が全焼しその他文化財6点も失われるという衝撃的なニュースが日本全国を駆け巡った。
この金閣寺放火事件は多くの小説家達に多大な影響を与え想像を駆り立てた。そしてその動機を探った。日本を代表する文豪三島由紀夫もその一人であった。今回はヘーゲル美学を交えながら本作「金閣寺」を考察していきたい
金閣寺放火事件について、水上勉が著書「金閣炎上」にて腐敗した寺のあり方、仏教のあり方の矛盾に対する復讐という人間的な動機を見出したのに対し、三島は本作にて金閣寺の普遍性こそが動機であったという前者に比べて形而上学的な分析を行った。普遍性を打ち壊す象徴的な出来事すなわち金閣寺の焼失によって、この社会のシステムすなわち世界そのものに挑戦しようとしたのではないか、というのである。では、簡単にあらすじに触れておこう。
生来の吃音(どもり)という極度のコンプレックスと父母からの期待を背負い、金閣寺に修行僧として入寺する主人公溝口。彼は幼い頃から金閣寺を「美」の象徴として認識し、心の支えとしてきた。しかし、唯一無二の親友の死、権威のあり方や女の内面の醜さに直面した溝口の陰鬱な少年時代はその想いを破壊への衝動へと駆り立てていく。ーー
本作は一貫して金閣寺の普遍性についての言及が随所に見られ、徐々にその動機にせまってゆく。この放火事件に至るまでの第一の伏線として第2章にて戦争により普遍性を失いつつある金閣寺への言及を行っている。
「…金閣というこの半ば永遠の存在と空襲の災禍とは、私の中でそれぞれ無縁のものでしかなかった。……しかし、やがて金閣は、空襲の火に焼き亡ぼされるかもしれぬ。…」
「金閣は私たちと同じ突端に立っていて、対面し、対話した。空襲の期待が、こんなにも私たちとを近づけた。……今まではこの建築の、不朽の時間が私を圧し、私を隔てていたのに、やがて焼夷弾の火に焼かれるその運命は、私たちの運命にすり寄ってきた。金閣はあるいは私たちより先に滅びるかもしれないのだ。すると金閣は私たちと同じ生を生きているように思われた。」
しかし、終戦と同時に溝口と金閣寺を繋いでいた「私を焼き亡ぼす火は金閣をも焼き亡ぼすだろうという」共通の危機の共有は潰えてしまう。敗戦という今までの日本の普遍性を根本から覆す経験。一方で世界が刻々と変化する中でその変化からは全く超然として「普遍性」を体現する金閣寺の対照性は溝口の心に大きな相反する想いを駆り立てた。
「敗戦の衝撃、民族的悲哀などというものから、金閣は超絶していた。…きのうまでの金閣はこうではなかった。とうとう空襲に焼かれなかったこと、今日からのちはその惧れがないこと、このことが金閣をして、再び、『昔から自分はここに居り、未来永劫ここに居るだろう』という表情を、取り戻させたのにちがいない。」
「『金閣と私との関係は絶たれたんだ』と私は考えた。『これで私と金閣とが同じ世界に住んでいるという夢想は崩れた。…敗戦は私にとっては、こうした絶望の体験に他ならなかった。」
戦後、社会システムは覆され新たな社会システムが日本に居座ることとなる。そして、金閣寺と共に灰になるという運命を微かな夢としていた主人公溝口はより金閣寺への執着を深めていく。その一方で卑屈で陰鬱で独断的な溝口の行動や言葉を「現世の言葉に翻訳してくれた」唯一の親友鶴川の死や、金閣寺の老師からの破門に近い宣言、嫌悪感を抱き煩わしく思っている母親からの重い期待は彼を破滅的な衝動へと誘ってゆく。
「…『金閣が焼けたら……、金閣が焼けたら、こいつらの世界は変貌し、生活の金科玉条はくつがえされ、列車時刻表は混乱し、こいつらの法律は無効になるだろう。』…」
「私はこの行為によって、金閣の存在する世界を、金閣の存在しない世界へ押しめぐらすことになろう。世界の意味は確実に変わるだろう。……思うほどに私は快活になってゆく自分を感じた。今私の身の回りを囲み私の目が目前に見ている世界の、没落と終結は程近かった。…金閣を載せた世界は、指のあいだをこぼれる砂のように、刻一刻、確実に落ちつつあった。……」
前述の「金閣炎上」で言及された老師をはじめとする金閣寺内部の腐敗を動機とした分析に以下の文言を以て三島は対抗する。
「…それまでにも老師をころそうという考えは全く浮かばぬではなかったが、忽ちその無効が知れた。…おしなべて生あるものは厳密な一回性を持っていなかった。…殺人が対象の一回性を滅ぼすためならば、殺人とは永遠の誤算である。…金閣を焼けば、それは純粋な破壊、とりかえしのつかない破壊であり、人間の作った美の総量の目方を確実に減らすことになるのである。」
簡単に解説すると、たとえ汚職を行っている老師一人を殺したところで、新たな僧侶がその地位に就き、その者がまたも汚職を行っていれば、それは本質的に老師を殺したとは言えない。生あるものは無限に増殖するのである。しかしながら、金閣寺は代替不可能な唯一無二の芸術作品である。もし金閣寺が失われてしまったとして何が代わりになることができよう。すなわち、命よりも金閣寺の美が失われてしまうことの方が厳密に言えば一回性という点で取り返しがつかない、というのである。生命至上主義の現代にはなんとも皮肉な動機とも言えるのではないだろうか。
以上の引用から、金閣寺はその美の中に秘めた普遍性こそが焼失の原因であったと捉えることができる。
この三島の議論についての考察に移る前に、この一般的に受け入れがたい金閣寺放火の動機理解への一助として美の定義とはなにか、ヘーゲル美学を参照しておきたい。彼は芸術終焉論の中で以下のような興味深い議論を行っている。
美すなわち芸術とは、本質的な点で哲学と使命は一致している。云わば、「唯一真にして“永遠の道具”」であるというのである。では、その使命とはなんなのか。それは真理表現である。芸術は感性的に、哲学は概念的にその真理を呈示するという点で異なる、というのである。
簡単に一例を挙げるとすれば、「神の崇高性」を呈示したものとしてはミケランジェロの『天地創造』、そして哲学書であればアウグスティヌス著の『告白』があるが、この二者は表現方法は違うものの、同じある一つの真理を我々に提示している。
すなわち裏返すならば、右から左に模写したに過ぎない単純な風景画や人物画等は芸術とは言えないといってもよい。そのものが真理を体現していることこそが、芸術の条件であるのだ。
では、今回の金閣寺という芸術作品についての考察をしていきたいと思う。金閣寺は悠久の時を超えてゆく中でその「普遍性」という真理を体現していた、と考えることができる。たしかに、製作当初、足利義満はこのような真理体現は予期しなかったかもしれない。この時点ではヘーゲルに言わせれば、芸術とは呼ぶことはできず、真の美の体現をすることはなかったであろう。しかしながら、悠久の時の中でゆっくりと静かに朽ちつつもその優美を体現していた金閣寺は製作者の意図を超えた真理を勝ち得たと考えられる。(放火事件当初、金閣寺の金箔は剥げ落ち老朽化がすすんだ簡素な風体をしていた。金閣寺の再建にあたり、金閣寺を1950年当初の姿に戻すのか、それとも建築された当初の姿に戻すのか議論があったものの後者が採択され今に至る。)
もしも、金閣寺が「普遍性」という真理を体現するに値しない芸術作品であれば、溝口の心にここまでの執着を持たせることは難しかったかもしれない。老師が殺害されていたかもしれない。ただ金箔を塗り付けた人工物に誰がこれほどまで愛着を持てよう。金閣寺はその意味で1950年に放火される直前こそがその美の最高潮にあったのであり、現在の再建された華やかな金閣寺にその美を求めることは難しいのかもしれない。つまり、溝口の「人類の美の総量を減らす」という第一の目論見はこの時点ではおよそ見事達成されたともいえる。
すなわち皮肉なことに、金閣寺はその「普遍性」を体現したがゆえに、その美は(芸術作品の寿命という観点からみれば)短命で終わるというおよそ「普遍性」とはかけ離れたところで終止符を打たれることとなったのである。
では、溝口の第二の目論見である金閣寺の焼失は世界を変えることができたのか。答えを先に言うならば、世界を変えることはできなかった。
私が思うに、この金閣寺焼失の奥に世界の変革を夢見たのは、実は主人公ではなく三島自身であったのではないか、と私は思う。これは、私の想像に過ぎないのであるが、三島は金閣寺の焼失に一種の希望を持っていたのではないか、という疑問が浮かんだ。
実は、著者三島由紀夫はこの著作を発表した十四年後の1970年に、戦後民主主義と日本国憲法への批判と自衛隊の国軍化を訴え、日本の自衛隊へ蜂起を訴えるものの失敗に終わり、公衆の面前で割腹自殺する。これは、当時大変衝撃的な事件であった。しかし、この事件すら、日本の社会システムを変えるに至らなかった。この事件を踏まえると、彼の著作である「金閣寺」は放火犯の告白文ではなく、日本の変革を願った三島のテーゼのように読むことができる。
そして、三島の想いとは裏腹に日本は米国の核の傘下という庇護の下で民主主義という名の衆愚政治を推し進め今に至るのである。
与えられた平和と民主主義の下で今の日本は本当に幸せなのだろうか。自分の国民と領土を自らの手で守ることを忘れ、ぬるま湯の中でふやけてしまった思想と政治と経済のみで我々は何を以て国際社会で闘っていけばよいのだろうか。平和であることが幸せの絶対条件としつつも、その平和は与えられた形でしか体現できない我々日本国民は本当に幸せなのだろうか。正義がどちらにあったかはさて置き、この腐りかけた国の中でもがき何とか日本を救おうと闘った者たちの存在を私たちは忘れてはならないと思う。
最後に「美と崇高の感情に関する観察」というカントの引用でこの書評を終え、三島と溝口への餞としたいと思う。
「戦争すら、秩序を保ちまた国民法の神聖を認めてこれを尊重しつつ遂行される限り、やはり何かしらの崇高性を持つ。…これに反して長期にわたる平和は、商人気質をこそ旺盛にするが、しかしそれと共に卑しい利己心、怯懦や懦弱の風をはこびらせ、国民の心意を低劣にするのが一般である。」
彼らは今の日本に何を想うのだろうか。