引越しのお知らせです。
大変お久しぶりです。
かれこれ4年近く前に書いていたブログですが、未だに今月だけでもすでに500人以上の人が見て下さってた事に驚いています。
全然更新できておらず、ごめんなさい。
そして有難うございました。
とある女子大生だった私もいつの間にやら、とあるサラリーマンになってしまいました。
得たもの、失くしてしまったもの、甘い想い、苦い想い、色んなことがありました。自分の昔の文章を読み返すと学問への荒削りで傲慢な情熱がぶつけられていて恥ずかしいと同時にもうこんな文章は書けないんだろうな、とも思います。
そんな中で最近あるきっかけがあり、また文章を書いてみようとふと思い立ち、昔に書いたものをせっせとこちらへお引越ししております。
あと、簡単な自己紹介も載せてます。もし興味を持ってくださった方が居れば覗きに来てください。
ある程度終えたらこっちで新しい読書感想文や、映画や絵の感想も投稿していきたいと思います。
またよろしくお願いします。
「バビロニアのくじ」J.L.ボルヘス (「伝奇集」より)
人生を語る上で、偶然というものは非常に大きな役割を担っている。私たちは生誕から死まで、確実性を持ち保障されることは何一つない。生まれた瞬間から、国籍、性別、容姿、貧富の差などをはじめとする努力や人智を超えた偶然の格差の元で生まれ、その後も終わりのない偶然の繰り返しの中で我々は一生を終える。この偶然という自然的な性質はカオス的な宇宙の性質の一つの表層であり、そこにひとつの我々と宇宙を繋ぐ物理学的な性質を越えた世界の様相を垣間見ることとなる。
こうして考えてみると、我々の積み上げてきた人生は「偶然、“運がよかった(ないし悪かった)”」の一言で片づけられてしまうこととなる。だからこそ人類はその偶然性からの脱却すべく、偶然に満ちた世界への対抗手段として数千年かけて哲学を通して「普遍性」の探究が熱心に行われたと考えることもできるかもしれない。しかし、人類というものは興味深いことに、この動きと真逆の動きである「さらなる偶然性の強化」というものに対しても古くから魅力を感じていることも事実である。その代表的なものの一つとして、「くじ」を挙げることができる。この起源は紀元前にまで遡ることができる。 “自ら選択して” 偶然に自らの運命を委ねるという行為は矛盾性を孕むように思われるが、本質的には世界の性質としてはなんとも理にかなっているのかもしれない。
今回の著書、「バビロニアのくじ」はタイトルから類推されるようにバビロニアにおける「くじ引き」の誕生からそのくじが国の在り方を支配するに至るまでのプロセスを伝承的に語っているのが本作である。念のために触れておくがこのプロセスは史実に基づいて描かれているわけではない。「事実のメカニズムには興味がない」という著者ボルヘスは文学の使命を史実ではなく美的事実の発見にあるとしている。この考えこそが彼の文体に幻想性を与えたに違いない。
では、早速「バビロニアのくじ」の内容に触れていきたい。その昔、バビロニアにてくじは庶民の遊びであった。しかしそのくじには、外れくじがなく「精神的価値を欠いていた」。このくじの失敗からくじ引きに改革が行われ、ある金額を手に入れるか、しばしば相当の額にのぼる罰金を払うか、という運試しへと様相を変えた。この改革は大衆を「くじ引き」に熱中させ、くじに加わらない者とくじに外れた者は軽蔑を受けることとなる。そしていつからか、このくじ引きを取り仕切る「講社」という存在が現れ、世俗的な権力と共に宗教的な権力を持つこととなる。大衆は、このくじによって勝者と敗者の二つに割れくじ引きには一種の神聖な意味と共に世俗的支配をも強めてゆく。その中で、ある一つの推論がくじの試行を無限回繰り返す改革へと誘うこととなる。
「仮にくじ引きが偶然の強化、宇宙の内部への混沌の定期的な侵出なのであるならば、偶然がくじ引きのひとつの段階ではなく、あらゆる段階に干渉するのはむしろ好都合ではないか?偶然がある者の死を命じながら、その死の情況は偶然に従わないというのは、おかしくはないか?」
「まず、一回目のくじ引きを想像してみよう。それは一人の男の死を宣告する。その遂行の為に、さらにもう一度くじ引きがが行われ、これが(たとえば)九人の死刑執行者を挙げたとする。これらの執行者のうち、四名が死刑執行人の名前を教える三回目のくじ引きを行ってもよい。……これが象徴的な大要である。現実にはいかなる決定も最終的ではなく、すべてが別の決定へと分岐してゆく。…」
皮肉なことに、「ささやかな冒険」として生み出された金銭を賭けた娯楽が、大衆の生活そして国家のシステムをも変革させていき、いつしか史実すらも捻じ曲げてしまう。くじ引きの権威と重要性が増すにつれて、くじそれ自体とそのシステムを管理し運営する「講社」の存在はより曖昧になってゆく。そして、最後にはこれら講社の存在をはじめとするバビロニアの史実すらも曖昧で偶然の産物に過ぎないかもしれない、というなんとも皮肉な終わり方をする。
ボルヘスの「伝奇集」には今回取り上げた「バビロニアのくじ」に加えて、17の短編作品が収録されており「バベルの図書館」や「円環の廃墟」などの名高い作品も収録されている。私はその中で敢えてこの「バビロニアのくじ」を取り上げた理由は二つある。
第一には冒頭に論じた偶然性というものの議論の面白さにある。確かに、我々の人生そのものは偶然に満ちており今行っているこの思考すらもただの偶然の重なりに過ぎないかもしれない。今まで積み上げてきたものも全てが自分の努力ではなくただ運が良かっただけで何一つ自分の力ではなかったのかもしれない。(一方ですべてが始まる前から決まっており、偶然など何一つないという宿命論というものもあるが、居心地のよい議論ではないことは確かである。)
しかしその一方で文明の高度化が進めば進むほど我々は自然の一部であるということを忘れてしまう。せめて自分がまだ実は自然の一部であると自覚するのは食と排泄くらいに限られてしまっているのではないだろうか。しかしながら、一度この偶然性というところに想いを廻らせば、人類同士の優劣などすべて平準化され、自分にも宇宙と同じように法則が適応されていることを考えることができる。ここに我々人間が「偶然性の強化」というところに魅力を感じる理由の一つがあるかもしれない。
そして、第二には人間の愚かさでもあり知性の象徴でもある、社会システムを生み出す上での人類特有の性質が如実に表現されていたことにある。
あらすじに戻って考えてみると、くじとはあくまで人類が生み出したものであるにも関わらず、いつの間にかそのシステムそのものがバビロニアの人のあり方や個々人の人生を規定するようになり、国家権力すらをも握るようになる。誰にもその偶然性から脱却でき得る者はいない。そして、このシステムが成熟するに連れてそのものを司る支配機構の存在すらも曖昧になってゆくのである。
この構図は、宗教や金におもしろいほど綺麗に符合する。神や金は人類がその利便性や精神性故に生み出したものである。ここに人間のみがもつ知性を垣間見ることができることも事実である。しかしながら、同時にそのコントロールができなくなってしまっていることも事実である。この地上に誰一人として、イスラム教とユダヤ教とキリスト教の三者を和解させることができる者も、為替を意のままに操ることができる者も存在しない。そして全世界の神や金銭を支配する機構というものも曖昧であることは言うまでもない。「バビロニアのくじ」にて、バビロニア人自身が生み出した「くじ」というシステムがいつの間にかバビロニア人自身を罰金にはじまり投獄や、死刑までも宣告できるほどの威力を持つようになるプロセスは、宗教における異端尋問や魔女狩り(現在もタンザニアでは魔女狩りが行われている。)やマネーゲームに負けた者の末路などに酷似する点がある。我々人間は自分の手で生み出したものに飲み込まれつつあるのである。
この「自分自身の手で生み出したものが支配できなくなる」という現状を考える為には、なにもSF映画にでてくるアンドロイドのクーデターのようなものを引き合いに出す必要などない。すでに我々はその中に飲み込まれているのだから。しかしながら、愚かなことに2045年問題に危機感を持つ者は居ても、宗教や金銭のコントロールを失った現代のあり方に危機感を持つ者は少ない。「バビロニアのくじ」に登場した衆愚的なバビロニア人の思慮の浅さに閉口する我々も同じような現状にいるということ胸に刻むべきであろう。

「金閣寺」三島由紀夫
1950年7月、ある一人の僧侶の放った炎によって金閣寺が全焼しその他文化財6点も失われるという衝撃的なニュースが日本全国を駆け巡った。
この金閣寺放火事件は多くの小説家達に多大な影響を与え想像を駆り立てた。そしてその動機を探った。日本を代表する文豪三島由紀夫もその一人であった。今回はヘーゲル美学を交えながら本作「金閣寺」を考察していきたい
金閣寺放火事件について、水上勉が著書「金閣炎上」にて腐敗した寺のあり方、仏教のあり方の矛盾に対する復讐という人間的な動機を見出したのに対し、三島は本作にて金閣寺の普遍性こそが動機であったという前者に比べて形而上学的な分析を行った。普遍性を打ち壊す象徴的な出来事すなわち金閣寺の焼失によって、この社会のシステムすなわち世界そのものに挑戦しようとしたのではないか、というのである。では、簡単にあらすじに触れておこう。
生来の吃音(どもり)という極度のコンプレックスと父母からの期待を背負い、金閣寺に修行僧として入寺する主人公溝口。彼は幼い頃から金閣寺を「美」の象徴として認識し、心の支えとしてきた。しかし、唯一無二の親友の死、権威のあり方や女の内面の醜さに直面した溝口の陰鬱な少年時代はその想いを破壊への衝動へと駆り立てていく。ーー
本作は一貫して金閣寺の普遍性についての言及が随所に見られ、徐々にその動機にせまってゆく。この放火事件に至るまでの第一の伏線として第2章にて戦争により普遍性を失いつつある金閣寺への言及を行っている。
「…金閣というこの半ば永遠の存在と空襲の災禍とは、私の中でそれぞれ無縁のものでしかなかった。……しかし、やがて金閣は、空襲の火に焼き亡ぼされるかもしれぬ。…」
「金閣は私たちと同じ突端に立っていて、対面し、対話した。空襲の期待が、こんなにも私たちとを近づけた。……今まではこの建築の、不朽の時間が私を圧し、私を隔てていたのに、やがて焼夷弾の火に焼かれるその運命は、私たちの運命にすり寄ってきた。金閣はあるいは私たちより先に滅びるかもしれないのだ。すると金閣は私たちと同じ生を生きているように思われた。」
しかし、終戦と同時に溝口と金閣寺を繋いでいた「私を焼き亡ぼす火は金閣をも焼き亡ぼすだろうという」共通の危機の共有は潰えてしまう。敗戦という今までの日本の普遍性を根本から覆す経験。一方で世界が刻々と変化する中でその変化からは全く超然として「普遍性」を体現する金閣寺の対照性は溝口の心に大きな相反する想いを駆り立てた。
「敗戦の衝撃、民族的悲哀などというものから、金閣は超絶していた。…きのうまでの金閣はこうではなかった。とうとう空襲に焼かれなかったこと、今日からのちはその惧れがないこと、このことが金閣をして、再び、『昔から自分はここに居り、未来永劫ここに居るだろう』という表情を、取り戻させたのにちがいない。」
「『金閣と私との関係は絶たれたんだ』と私は考えた。『これで私と金閣とが同じ世界に住んでいるという夢想は崩れた。…敗戦は私にとっては、こうした絶望の体験に他ならなかった。」
戦後、社会システムは覆され新たな社会システムが日本に居座ることとなる。そして、金閣寺と共に灰になるという運命を微かな夢としていた主人公溝口はより金閣寺への執着を深めていく。その一方で卑屈で陰鬱で独断的な溝口の行動や言葉を「現世の言葉に翻訳してくれた」唯一の親友鶴川の死や、金閣寺の老師からの破門に近い宣言、嫌悪感を抱き煩わしく思っている母親からの重い期待は彼を破滅的な衝動へと誘ってゆく。
「…『金閣が焼けたら……、金閣が焼けたら、こいつらの世界は変貌し、生活の金科玉条はくつがえされ、列車時刻表は混乱し、こいつらの法律は無効になるだろう。』…」
「私はこの行為によって、金閣の存在する世界を、金閣の存在しない世界へ押しめぐらすことになろう。世界の意味は確実に変わるだろう。……思うほどに私は快活になってゆく自分を感じた。今私の身の回りを囲み私の目が目前に見ている世界の、没落と終結は程近かった。…金閣を載せた世界は、指のあいだをこぼれる砂のように、刻一刻、確実に落ちつつあった。……」
前述の「金閣炎上」で言及された老師をはじめとする金閣寺内部の腐敗を動機とした分析に以下の文言を以て三島は対抗する。
「…それまでにも老師をころそうという考えは全く浮かばぬではなかったが、忽ちその無効が知れた。…おしなべて生あるものは厳密な一回性を持っていなかった。…殺人が対象の一回性を滅ぼすためならば、殺人とは永遠の誤算である。…金閣を焼けば、それは純粋な破壊、とりかえしのつかない破壊であり、人間の作った美の総量の目方を確実に減らすことになるのである。」
簡単に解説すると、たとえ汚職を行っている老師一人を殺したところで、新たな僧侶がその地位に就き、その者がまたも汚職を行っていれば、それは本質的に老師を殺したとは言えない。生あるものは無限に増殖するのである。しかしながら、金閣寺は代替不可能な唯一無二の芸術作品である。もし金閣寺が失われてしまったとして何が代わりになることができよう。すなわち、命よりも金閣寺の美が失われてしまうことの方が厳密に言えば一回性という点で取り返しがつかない、というのである。生命至上主義の現代にはなんとも皮肉な動機とも言えるのではないだろうか。
以上の引用から、金閣寺はその美の中に秘めた普遍性こそが焼失の原因であったと捉えることができる。
この三島の議論についての考察に移る前に、この一般的に受け入れがたい金閣寺放火の動機理解への一助として美の定義とはなにか、ヘーゲル美学を参照しておきたい。彼は芸術終焉論の中で以下のような興味深い議論を行っている。
美すなわち芸術とは、本質的な点で哲学と使命は一致している。云わば、「唯一真にして“永遠の道具”」であるというのである。では、その使命とはなんなのか。それは真理表現である。芸術は感性的に、哲学は概念的にその真理を呈示するという点で異なる、というのである。
簡単に一例を挙げるとすれば、「神の崇高性」を呈示したものとしてはミケランジェロの『天地創造』、そして哲学書であればアウグスティヌス著の『告白』があるが、この二者は表現方法は違うものの、同じある一つの真理を我々に提示している。
すなわち裏返すならば、右から左に模写したに過ぎない単純な風景画や人物画等は芸術とは言えないといってもよい。そのものが真理を体現していることこそが、芸術の条件であるのだ。
では、今回の金閣寺という芸術作品についての考察をしていきたいと思う。金閣寺は悠久の時を超えてゆく中でその「普遍性」という真理を体現していた、と考えることができる。たしかに、製作当初、足利義満はこのような真理体現は予期しなかったかもしれない。この時点ではヘーゲルに言わせれば、芸術とは呼ぶことはできず、真の美の体現をすることはなかったであろう。しかしながら、悠久の時の中でゆっくりと静かに朽ちつつもその優美を体現していた金閣寺は製作者の意図を超えた真理を勝ち得たと考えられる。(放火事件当初、金閣寺の金箔は剥げ落ち老朽化がすすんだ簡素な風体をしていた。金閣寺の再建にあたり、金閣寺を1950年当初の姿に戻すのか、それとも建築された当初の姿に戻すのか議論があったものの後者が採択され今に至る。)
もしも、金閣寺が「普遍性」という真理を体現するに値しない芸術作品であれば、溝口の心にここまでの執着を持たせることは難しかったかもしれない。老師が殺害されていたかもしれない。ただ金箔を塗り付けた人工物に誰がこれほどまで愛着を持てよう。金閣寺はその意味で1950年に放火される直前こそがその美の最高潮にあったのであり、現在の再建された華やかな金閣寺にその美を求めることは難しいのかもしれない。つまり、溝口の「人類の美の総量を減らす」という第一の目論見はこの時点ではおよそ見事達成されたともいえる。
すなわち皮肉なことに、金閣寺はその「普遍性」を体現したがゆえに、その美は(芸術作品の寿命という観点からみれば)短命で終わるというおよそ「普遍性」とはかけ離れたところで終止符を打たれることとなったのである。
では、溝口の第二の目論見である金閣寺の焼失は世界を変えることができたのか。答えを先に言うならば、世界を変えることはできなかった。
私が思うに、この金閣寺焼失の奥に世界の変革を夢見たのは、実は主人公ではなく三島自身であったのではないか、と私は思う。これは、私の想像に過ぎないのであるが、三島は金閣寺の焼失に一種の希望を持っていたのではないか、という疑問が浮かんだ。
実は、著者三島由紀夫はこの著作を発表した十四年後の1970年に、戦後民主主義と日本国憲法への批判と自衛隊の国軍化を訴え、日本の自衛隊へ蜂起を訴えるものの失敗に終わり、公衆の面前で割腹自殺する。これは、当時大変衝撃的な事件であった。しかし、この事件すら、日本の社会システムを変えるに至らなかった。この事件を踏まえると、彼の著作である「金閣寺」は放火犯の告白文ではなく、日本の変革を願った三島のテーゼのように読むことができる。
そして、三島の想いとは裏腹に日本は米国の核の傘下という庇護の下で民主主義という名の衆愚政治を推し進め今に至るのである。
与えられた平和と民主主義の下で今の日本は本当に幸せなのだろうか。自分の国民と領土を自らの手で守ることを忘れ、ぬるま湯の中でふやけてしまった思想と政治と経済のみで我々は何を以て国際社会で闘っていけばよいのだろうか。平和であることが幸せの絶対条件としつつも、その平和は与えられた形でしか体現できない我々日本国民は本当に幸せなのだろうか。正義がどちらにあったかはさて置き、この腐りかけた国の中でもがき何とか日本を救おうと闘った者たちの存在を私たちは忘れてはならないと思う。
最後に「美と崇高の感情に関する観察」というカントの引用でこの書評を終え、三島と溝口への餞としたいと思う。
「戦争すら、秩序を保ちまた国民法の神聖を認めてこれを尊重しつつ遂行される限り、やはり何かしらの崇高性を持つ。…これに反して長期にわたる平和は、商人気質をこそ旺盛にするが、しかしそれと共に卑しい利己心、怯懦や懦弱の風をはこびらせ、国民の心意を低劣にするのが一般である。」
彼らは今の日本に何を想うのだろうか。
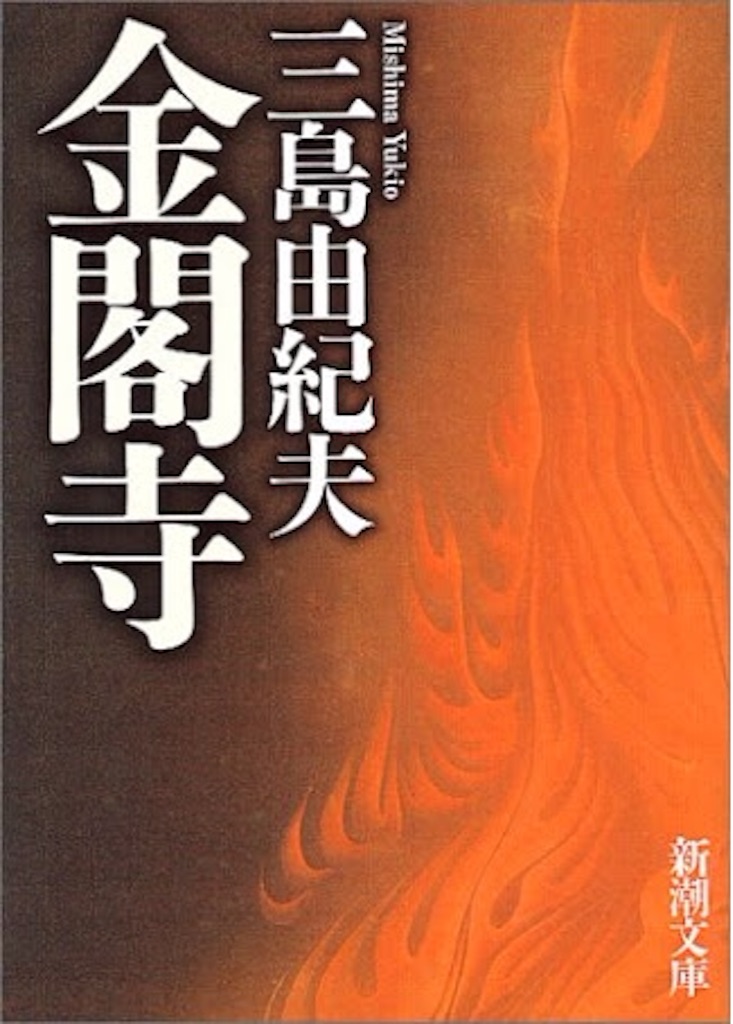
「イワン・イリッチの死」トルストイ
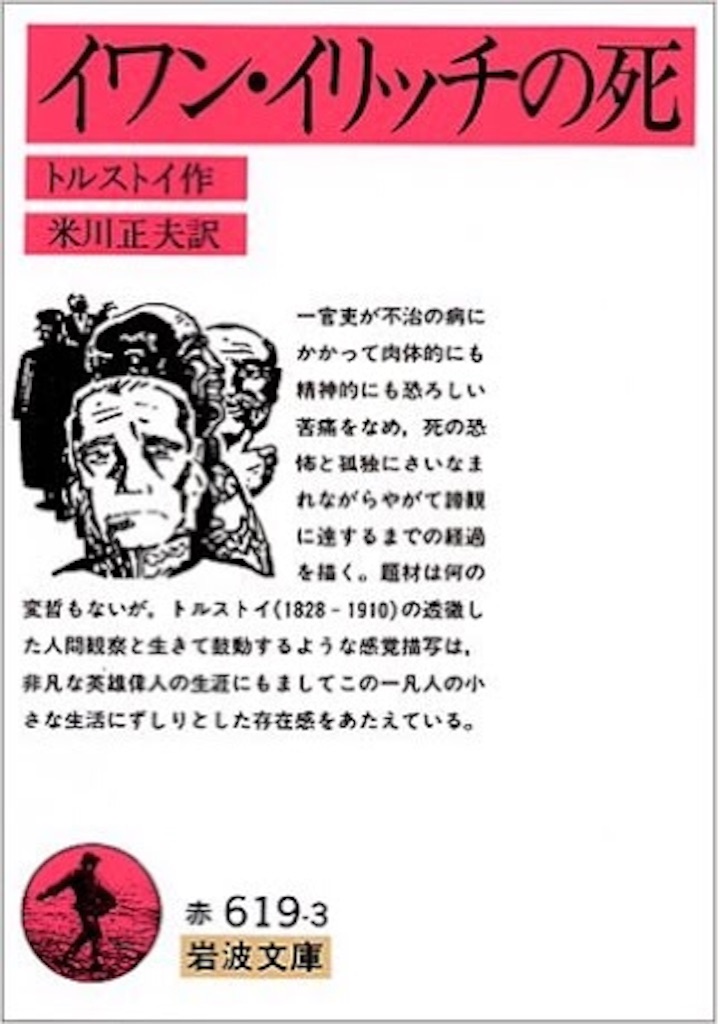
「脂肪の塊」モーパッサン
私がこの小説に出会ったのは高校の世界史の授業であった。世界各地域の文学作品を時代ごとに作者名と共に頭に叩き込むことにうんざりしている最中、この本のタイトルは強烈な印象を私の胸に残した。当時、一体どんな物語なのか想像を巡らしたものの実際に本を手に取るには至らなかった。
時は流れ、先日古本屋でこの「脂肪の塊」を見つけ四年の空白を越えて内容に触れるに至った。
舞台は普仏戦争の最中のフランス。プロシャ軍の占領地から脱出を目論んだ馬車に居合わせたブルジョアたちと一人の娼婦。その娼婦、あだ名を「ブール・ド・シェイフ」(脂肪の塊)という。逃亡の最中、彼女を見初めた敵将校はブール・ド・シェイフが自分と一夜を共にするまで一行の逃亡を認めない、という要求を受ける。愛国心が強く頑なに要求を断る彼女にブルジョアたちは態度をガラリと変え彼女に説得を試みる。――
モーパッサンの処女作として名高いこの「脂肪の塊」は一夜にして彼を一流文豪にまで押し上げた。彼のまるで突き放すようなペシミズムは本作から一貫して彼の文学作品の随所に垣間見ることができる。正義や道理の通じない人間の理不尽な行動や、ちょっとした虚栄心やエゴイズムが招く運命のもつれを彼は淡々と第三者的なナレーションを以って語る。彼は一歩引いた目線からウィットにとんだ知的なユーモアセンスを用いて哀しいほどに滑稽な人間達を描く。私自身、モーパッサンの著作に大体30作品以上触れてきたが、彼の描く物語で一般的にいう「幸福な結末」といえるものに出会ったことがほとんどない。(トーマス・ハーディの執筆タッチに共通したものを感じるのは私だけだろうか?)
さて、本作の考察に移りたいと思う。
作者がブルジョアの語る愛国心や思想について如何に信頼を置かず、冷静に観察しているかが伺える。アメリカの経済学者であるジョン・K・ガルブレイスが「不確実性の時代」の植民化の思想の章にて語った一節に次のようなものがある。
「…植民地主義を正当化した思想は、決して正直であったとは言えない。…多くの事柄について、行動の背後にある理由は隠されたままのほうがよいということを、人々は承知している。神話があったほうが、良心は守られやすいのだ。そしてまた、他人を説得するためには、まず何よりも先に自分自身を説得しなければならない。神話は、戦争に関わるところでは特に重要であった。」
「人間は、自らの命を落とすためには、かなり高尚な動機を持つ必要がある。富や権力を、あるいは誰か他人の特権を守ったり高めたりする…そのために死ぬというのでは、美化のしようがない。」
「…植民主義の場合も同様である。そのための本当の動機を述べたとすれば、それはあまりに粗野で利己的で不愉快なものとなるだろう。…そのため、植民化を推進した人々は大抵の場合、-単なる経済的な理由でなく-自分たちの何か深遠な倫理観、精神的、社会的、あるいは政治的な価値の担い手としての役割を自認してきた。」
私は、本作を読みこの一節が想起された。
すなわち、ガルブレイスの理論を交えて話すならば、ブール・ド・シェイフがこの敵将校と一夜を共にするには、それ相応の高尚な思想が必要でありブルジョアたちは(なんとここには聖職者も混ざっている!)今までサロンなどで磨いてきた雄弁さと教養を活用して躍起になって彼女を説き伏せるのである。
ブール・ド・シェイフにあてつけた、聖職者と貴婦人のやりとりの一部を引用する。
「そう致しますと、あなた方聖職者様のお考えでは、神様はどんな手段でもお受け入れになって、動機さえ清らかであればお赦し下さるのですね?」
「誰がそれを疑えましょう!それだけでは非難される行いも、それを行わせた考えの如何によっては、しばしば賞賛に値するものとなります。」
この文言だけを見ると大層立派で上品な理論であるが、一歩踏み込めばそれは早く占領地から逃げ出したいブルジョアが自分の利益のために、ブール・ド・シェイフに代わって敵将校と寝るという「美化の仕様のない」醜い事実を「神」や「清らかさ」などにより覆い隠したに過ぎない。(ちなみにフランスでは敵軍との情事はご法度であり、二次大戦終結時にドイツ人と関係のあったフランス人女性は売国奴として丸坊主にされ、暴力を受けながら、鎖をつけて町中を練り歩かされた。)
こういった、支配者層の美しい言葉の裏にある人間的な醜い感情を、陳腐なあるいは下品な表現を一切することなく描き上げたモーパッサンの手腕には脱帽せざるを得ない。
これらの説得の結果、ブール・ド・シェイフは敵将校と一夜を共にし、馬車は出発する。しかし、同乗したブルジョアたちは彼女に軽蔑的な眼差しを送り、思わず彼女が悔し泣きをするところでストーリーは終わる。
ここまで読むと、痛烈なブルジョア批判に過ぎない小説となってしまうのだが、私が先ほどガルブレイスを引用したことには二つの意図がある。
まず一つは、すなわち「死」と「理論」の関係性の暗示である。
私は、この小説はただのブルジョア批判ではなく「理論」は「人を殺す」ことができる、というモーパッサンのテーゼのように感じるのである。
「理論」が「人を殺す」場面として、現在のイスラム教過激派のテロ、社会主義国内で行われた多くの残虐行為、世界史に残る血なまぐさい戦争など枚挙に暇がない。
しかし、それだけが理論が人を殺す瞬間ではないのではないか。
今回のストーリーでは、確かにブール・ド・シェイフは命を落としたわけでもなく、他に血なまぐさい事件も起こっていない。
しかしながら、ブルジョアたちの作り上げた表面上に崇高な「理論」こそがブール・ド・シェイフの高潔な愛国心と親切心を利用し文字通り「殺して」しまったのである。
これは、企業に働くサラリーマンをはじめとして現在の社会にも言える場面は多々あるのではないだろうか。
第二に、ここから類推するにこの小説は反戦小説なのではないか、という事である。
「理論」を信じ、身を捧げ、裏切られた一人の娼婦の物語の裏の意図に、政治家の「理論」を信じ、命を捧げる衆愚的な「大衆」の無知とその戦争を作り上げるシステム自体を皮肉的に描いているのではないだろうか。
こう類推する理由として、モーパッサンは最後の場面でブール・ド・シェイフへの憐れみや彼女の行いの正当性などを一切言及していない。ただ、冷淡な態度をとるブルジョアたちと涙を流す娼婦を淡々と描写するのみであった。加えて、モーパッサンは生涯を通して多くの反戦小説を残している。
私自身、この「理論」に踊らされている「大衆」になってはいないか、自省の念に駆られざるを得なかった。
「はじめに言葉ありき」
この言葉の妙を改めて実感する一作であった。

「車輪の下」ヘルマン・ヘッセ
ドイツの片田舎で神童と言われ育った主人公ハンスは全国のエリー
ヘッセをはじめとしてトマスマンらのドイツ文学の金字塔と言われ
さて、今回の主人公ハンスについて考察していきたいと思う。
彼は生来自然を愛する純朴な少年であった。
受験勉強を終え、
しかし、神学校にて目覚めた自我と周囲の期待との狭間でハンスの細い四肢
「あれほどの苦しみも、勉強も汗も、
ハンスは挫折とともに帰郷する。
その中で機械工という職につき、
しかし、その中でナンセンス的に訪れる「死」。
ハンスの葬式にて古くから親交のあった者は言う。
「みんなでやったんだ、あの子をこんなハメに落としたのは、
ここに、「車輪の下」
特に印象的だったのが文中、第五章はじめの作者の嘆きともとれる数行である。ヘッセは読者に問いかける。
「…だれひとりとして、このやつれた童心の哀れな微笑のうらに、
「…なぜ彼はもっとも感じやすい、
「過度に駆り立てられた子馬は、
私達も巨大な車輪の一部となり、
真の教育とはなんなのか、
今年で本作が執筆され110年の月日が流れた。
しかし、
ある時はニュースの中に、友人の中に、そして自分の中に。
